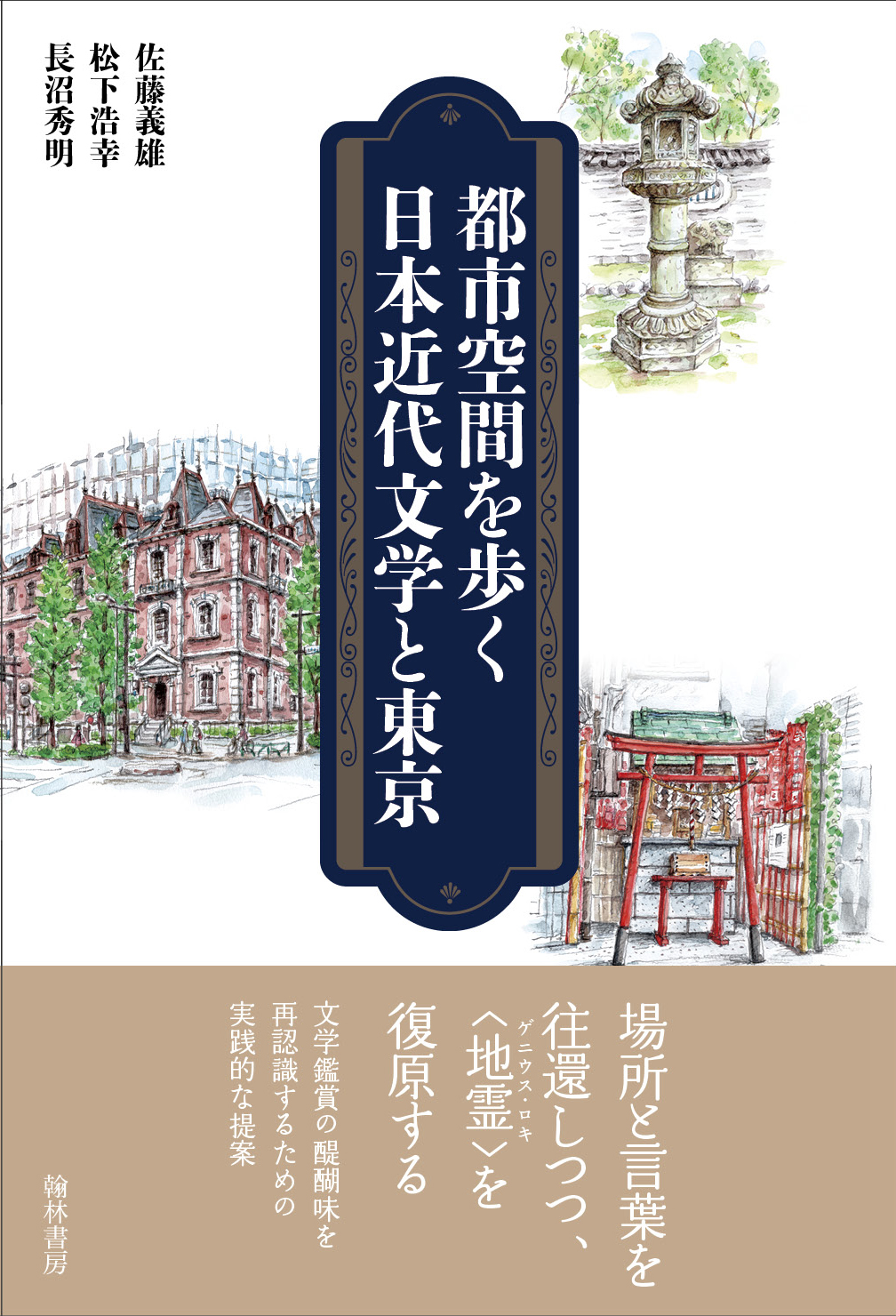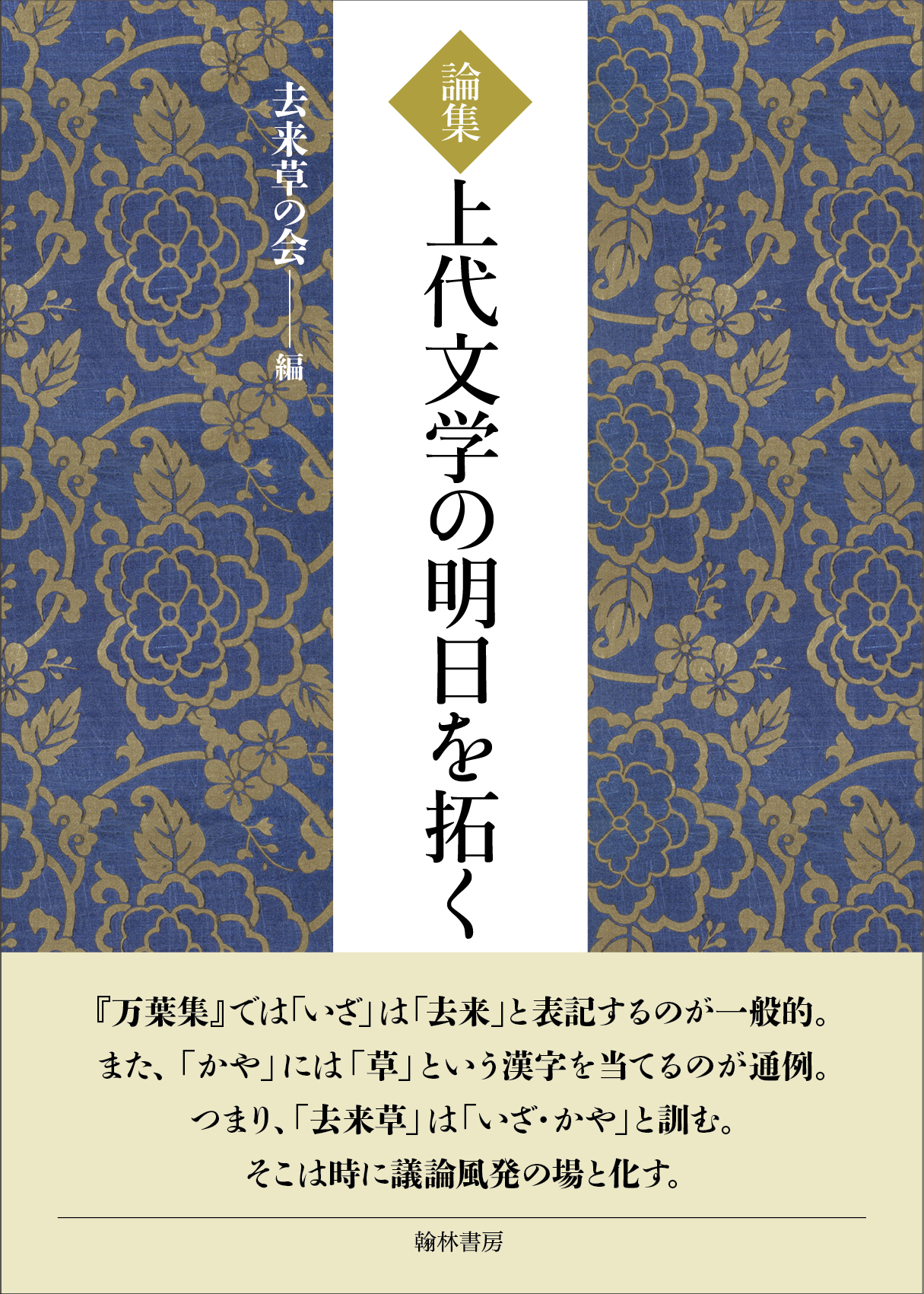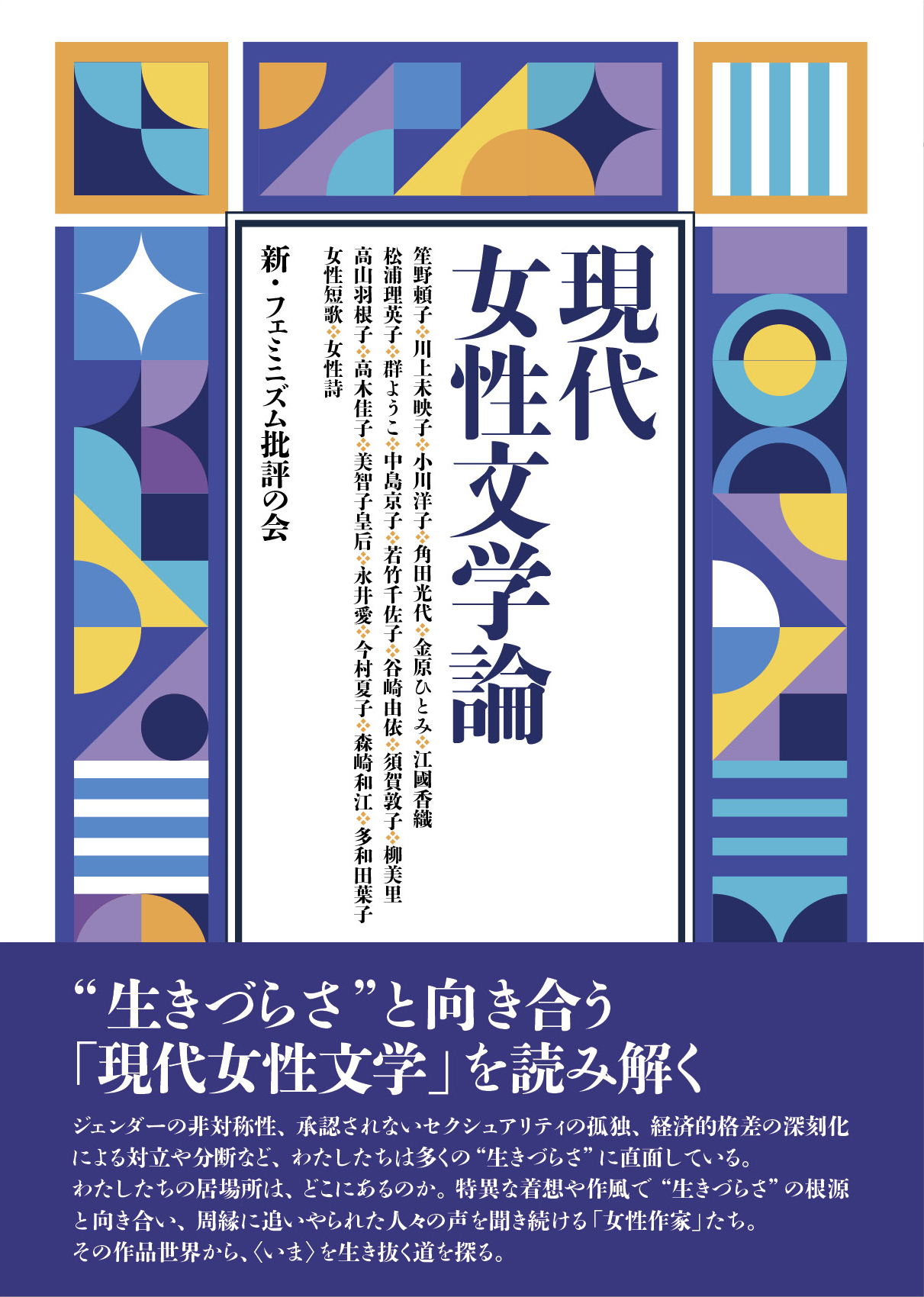『銀の匙』の魅力をもっと知りたい、
背景を探りたいと思われる方々に捧げる。
高島俊男氏から〈『銀の匙』にかかわることなら何でも調べてやろう、中勘助の見たものは何でもみてやろう、という意気ごみが好感が持てるし、ほほえましくもある〉(『ほめそやしたりクサしたり』)と評された『「銀の匙」考』の続報
Ⅰ 「銀の匙」注
英詩から原「銀の匙」へ
一 和辻哲郎「解説」/二 上田敏先生/三 山田又吉宛書簡/四 Wordsworth
「銀の匙」主人公の見た悪夢
〈駝鳥と人間の相撲〉注
オノマトペ〈たをたを〉
[コラム] 「銀の匙」に出てくる絵・本・話 補遺〔掛図の素材〕
〈やまかがし〉は無毒でない
[コラム ]〈貞ちやん〉は女の子か?
初出・初版「銀の匙」に登場するクリスチャンたち
一 小日向台町一丁目四番地/二 Christlieb夫妻/三 稲澤ゑい子/四 余録
Ⅱ 家族
御一新頃の〈父〉
中勘助と名古屋
〈伯母さん〉のお墓
一 潮見純子氏の教示/二 香川八重子氏の教示/三 齟齬/四 謎解き
[コラム] 〈兄〉伝メモ
Reader
〈末の妹〉と折紙
Ⅲ 恋
『提婆達多』の参考書
[コラム] 映画化されていた『提婆達多』
「菩提樹の蔭」と古典
一 本文/二 先行論文/三 大迦葉伝/四 『古今著聞集』/五 〈朝顔〉
黒い幕
〈妙子さん〉
中勘助小児愛者的傾向説の検討
仮説・青春期の恋
一 〈友達〉の〈姉様〉のモデル/二 関〔江木〕ませ/三 〈ななとせの昔〉/四 〈昔の人〉
仮説・朱夏期の恋
一 謎/二 私解/三 “泥中蓮”/四 仮説を使嗾する言動
仮説・白秋期の恋
一 仮説の暗号的証言/二 レクイエム/三 神経衰弱/四 龍女成仏
平塚の家
Ⅳ 戦争
末子頌
一 菊野美恵子氏の新見/二 野村家/三 勘助と松陰/四 末子と松陰
「光華門」注
[コラム] 静岡に出現したクダン
[コラム] 〈あれ寺の仁王はこけて梅の花〉
「古国の詩」の〈案内記〉
付
教科書に採られた中勘助作品
“高橋物語学”を相続する
『源氏物語』を結節点に、“高橋物語学”を特徴づける「遠近法」と「表現史」をみずからの課題として受け継いだ個性溢れる諸論稿による“星座”を、次代に向けて浮かびあがらせる試み。
いま、「高橋亨」を批判的に相続し、新たな研究の領野と地平を切り拓く。
はじめに
Ⅰ 〈語り〉と遠近法
『紫式部日記』における〈心〉への眼差し─心的遠近法の表現史の一端として◆加藤直志
天女の〈語り手〉─『源氏物語』初音巻冒頭を読む◆土居奈生子
予言する『源氏物語』─夕霧と源師房の遠近法◆安藤 徹
物語と映像の〈心的遠近法〉─『平家物語』「木曾最期」のアダプテーションとインターテクスチュアリティ◆高木 信
『児今参り物語』の〈語り〉─室町絵巻における『源氏物語』の享受と方法◆末松美咲
絵で語り、文字で描く─天理本『いはやものがたり』の絵・詞・画中詞◆江口啓子
Ⅱ 引用と表現史(1)―『源氏物語』以前
神人日本武尊─『日本書紀』のヤマトタケル◆稲生知子
『伊勢物語』五十段のなかの仏教─その「あだ」なるものの根拠◆咲本英恵
『うつほ物語』仲澄の死と手紙─『源氏物語』柏木を補助線として◆本宮洋幸
「かしづく」の語義とその展開◆東 望歩
「腹きたなし」という「継母」像の誕生─『源氏物語』「蛍」巻の「継母の腹きたなき昔物語も多かるを」を契機として◆畑 恵里子
『源氏物語』朝顔巻、『枕草子』雪山の段引用─「中宮の雪山作り」と亡霊と鎮魂◆橋本ゆかり
猫と暮らす人びと─『源氏物語』の女三宮が受け継ぐ財宝をめぐって◆亀田夕佳
Ⅲ 引用と表現史(2)―『源氏物語』以後
宇治大君の心中を語る歌ことば表現─「御すまひのかひなき山なしの花」◆内藤英子
宇治の中の君から『寝覚』の女君へ─〈女の生〉をめぐって◆乾 澄子
引用のテクスチュア─『源氏物語』浮舟巻・蜻蛉巻における〈憂し〉の物語◆本田恵美
平清盛と藤原道長─法華経供養の願文と表白から◆牧野淳司
諷喩としての「なよ竹物語」の語り─後嵯峨院の評価をめぐって◆中根千絵
『秋夜長物語』の表現と『太平記』─メトロポリタン美術館本を中心に◆鹿谷祐子
矢川澄子『兎とよばれた女』と高畑勲『かぐや姫の物語』における翻案─「自然な身体」からの離脱/への回帰◆西原志保
◆ ◆ ◆
『三体和歌』をめぐって◆高橋 亨
おわりに
場所と言葉を往還しつつ、〈地霊〉を復原する文学鑑賞の醍醐味を再認識するための実践的な提案
一 樋口一葉「日記」「別れ霜」
─東京図書館・お茶の水橋・万世橋
二 夏目漱石『それから』
─神楽坂・小石川・青山
三 森鷗外「百物語」
─向島
四 高村光太郎『智恵子抄』
─千駄木・日暮里
五 江戸川乱歩「目羅博士」
─上野・丸の内
六 長谷川時雨『旧聞日本橋』
─日本橋
七 徳冨蘆花『不如帰』
─赤坂氷川町
八 田山花袋『田舎教師』
─上野公園
九 久保田万太郎「春泥」
─日暮里
十 藤村「並木」と芥川「毛利先生」
─日比谷・大手町・神田
十一 永井荷風「紅茶の後」
─銀座
十二 三島由紀夫「詩を書く少年」
─目白・学習院
『万葉集』では「いざ」は「去来」と表記するのが一般的。
また、「かや」には「草」という漢字を当てるのが通例。
つまり、「去来草」は「いざ・かや」と訓む。
そこは時に議論風発の場と化す。
◆ 行間を埋める旅
──戦後の万葉研究史の片隅で/梶川信行
◆ イシコリドメと鏡作連/工藤 浩
◆ ヌナトモモユラニ考
──玉・刀剣にわたる定型化をめぐって/鈴木雅裕
◆ 文学発生論を振り返る
──歌表現の自立に関して/山崎健太
◆ 勤しみ、嘆き、うたう舎人
──舎人等慟傷作歌二十三首について/影山尚之
◆ 山部宿禰赤人が歌六首/鈴木崇大
◆ 「歌集」のテキスト性をめぐって
──『万葉集』巻六終末部における「重層性」を手がかりに/大浦誠士
◆ 大伴坂上郎女と宴席
──方法論の視座として/野口恵子
◆ 『八犬伝』における記紀神話の出典コンテクスト
──本居宣長『古事記伝』「直毘霊」と冤・冤枉・冤枉神/藏中しのぶ
“生きづらさ”と向き合う
「現代女性文学」を読み解く
ジェンダーの非対称性、承認されないセクシュアリティの孤独、経済的格差の深刻化による対立や分断など、わたしたちは多くの“生きづらさ”に直面している。
わたしたちの居場所は、どこにあるのか。特異な着想や作風で“生きづらさ”の根源と向き合い、周縁に追いやられた人々の声を聞き続ける「女性作家」たち。
その作品世界から、〈いま〉を生き抜く道を探る。
Ⅰ ───越境・攪乱するジェンダー/セクシュアリティ
Ⅱ───変容する家族とケアの倫理
Ⅲ───紡がれる記憶/記憶の継承
Ⅳ───短歌・演劇表現から探る現代
文学は権力と主体の関係(主体化=権力化)をどのように描いてきたのか。
夏目漱石、森鷗外、伊藤左千夫、横光利一、坂口安吾、中野重治、遠藤周作らの文学を縦横に論じて、文学と権力の本質に迫る。
「中本たか子小伝」を付す。
はじめに─芥川龍之介「鼻」に触れつつ
Ⅰ────漱石文学の応答責任
転移する「こころ」
手記の宛先
「坊つちやん」の応答責任
漱石文学の謎 1「こころ」のハムレット/2先生の最期/3「蛇」のサブリミナル
Ⅱ────文学と権力
「高瀬舟」の〈他者〉
「野菊の墓」の寓意
「マルクスの審判」の正義
権力の表現 1「入れ札」の天皇/2「恋するザムザ」の欲望
Ⅲ────戦後の風景
「萩のもんかきや」私注
「海と毒薬」と同時代
「桜の森の満開の下」の主体─「羅生門」を合わせ鏡として
Ⅳ────表現の横断
表現の自由をめぐって
年上の女が先に死ぬ物語
近代の恐怖表象
Ⅴ────中本たか子の時代
生い立ちと上京 中本たか子小伝(一)
活躍と左傾 中本たか子小伝(二)
拷問と入院 中本たか子小伝(三)
服役と再出発 中本たか子小伝(四)
戦中と終戦 中本たか子小伝(五)
資料紹介 中本たか子の書簡
泉鏡花、宮澤賢治、坂口安吾、太宰治などの作品をそれぞれ夢、香り、異界、はなしといったキイワードから読み、後半では新劇の展開を、岸田國士、田中千禾夫、矢代静一、井上ひさしなどの戯曲や岡本かの子の小説などから辿ってみる。
Ⅰ─フィクションの生まれるところ
第一章 開かれた夢の力─泉鏡花「春昼」「註文帳」など
第二章 植物性の恋物語─宮澤賢治「ローマンス」をめぐって
第三章 モダニストの一軌跡─富ノ澤麟太郎とその周辺
第四章 一九三〇年代・パリの日本語─横光利一・林芙美子・森三千代の場合
第五章 フィクションとしての異界─桜の森と夜長の里
第六章 「はなし」を受け継ぐ─太宰治「破産」
Ⅱ─劇の生まれるところ
第七章 「タンタジールの死」の上演をめぐって─自由劇場・友達会の取り組み
第八章 田漢の見た日本の新劇とその影響
第九章 戯曲のことばと劇場空間─岸田國士「ママ先生とその夫」「犬は鎖に繋ぐべからず」
第一〇章 ダンスへの目覚め─岡本かの子「やがて五月に」から
第一一章 神に問うことば─田中千禾夫と矢代静一
第一二章 音楽劇における歌のはたらき─井上ひさし「太鼓たたいて笛ふいて」
女性たちは何を書いてきたのか
階級、ジェンダー、セクシュアリティなどの視座から、女性文学の多様な側面に切り込む。宮本百合子を中心に、大塚楠緒子、野上彌生子、平塚らいてう、岡本かの子、林芙美子、石牟礼道子、向田邦子、角田光代らの作品を幅広く取り上げ、一世紀にわたる女性文学の内実を解き明かす、フェミニズム批評の実践。
Ⅰ
一 フェミニズム批評
第1章 女と言説
第2章 フェミニズム批評の有効性
第3章 フェミニズム批評・ジェンダー批評・ケアの倫理
第4章 女性文学史の新たな構築をめざして—『【新編】日本女性文学全集』全一二巻完結
Ⅱ
二 宮本百合子とセクシュアリティ
第5章 百合子とセクシュアリティ—レズビアン表象の揺らぎ
第6章 『伸子』の素子—レズビアニズムの〈変態〉カテゴリー化に抗して
第7章 『乳房』—ジェンダー・セクシュアリティの表象
第8章 鼎談 愛と生存のかたち—湯浅芳子と百合子の場合(黒澤亜里子・沢部ひとみ・岩淵宏子)
三 宮本百合子と反戦・平和
第9章 『杉垣』にみる反戦表現—国策にあらがう〈居据り組〉夫婦
第10章 『築地河岸』『二人いるとき』—既婚女性と反戦
第11章 『鏡の中の月』『雪の後』『播州平野』をめぐって—戦争ファシズムと女性
第12章 占領下の百合子—民主化・女性の独立・反戦平和をめざして
四 宮本百合子の世界と表現方法
第13章 百合子と日本女子大学校
第14章 『伸子』—研究の変遷と今日的争点
第15章 『伸子』にみるスペイン風邪と恋—パンデミックと文学
第16章 『未開な風景』—テーマ・創作方法をめぐって
第17章 宮本百合子と佐多稲子—表現方法の差異と多様性
Ⅲ
五 女性表象の変容
第18章 女性による樋口一葉論—三宅花圃・田辺夏子・与謝野晶子・平塚らいてう・田村俊子・長谷川時雨
第19章 大塚楠緒子『空薫』『そら炷 続編』—反家庭小説の試み
第20章 野上彌生子『噂』—揺れる家庭
第21章 求愛の表現—樋口一葉・田村俊子・宮本百合子・山田詠美
第22章 戦時下の「母性」幻想—総力戦体制の要
第23章 角田光代『八日目の蟬』にみる母と娘—母性幻想の終焉
六 フェミニズムとセクシュアリティ
第24章 『青鞜』におけるセクシュアリティの政治学への挑戦—貞操・堕胎・廃娼論争
第25章 平塚らいてうと成瀬仁蔵—『青鞜』と日本女子大学校
第26章 平塚らいてう—出発とその軌跡
第27章 田村俊子宛鈴木悦書簡をめぐって
第28章 林芙美子『ボルネオ ダイヤ』『牛肉』『骨』—売春婦たちの〈掟〉
第29章 林芙美子『晩菊』—〈老い〉とセクシュアリティ
七 社会とジェンダー
第30章 岡本かの子『生々流轉』—乞食の意味
第31章 石牟礼道子の世界—表象としての〈水俣病〉
第32章 三浦綾子『細川ガラシャ夫人』—宗教的女性像
第33章 向田邦子のまなざし—『お辞儀』『スグミル種』『はめ殺し窓』を読む